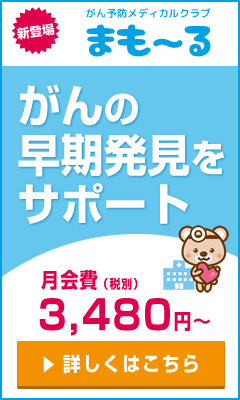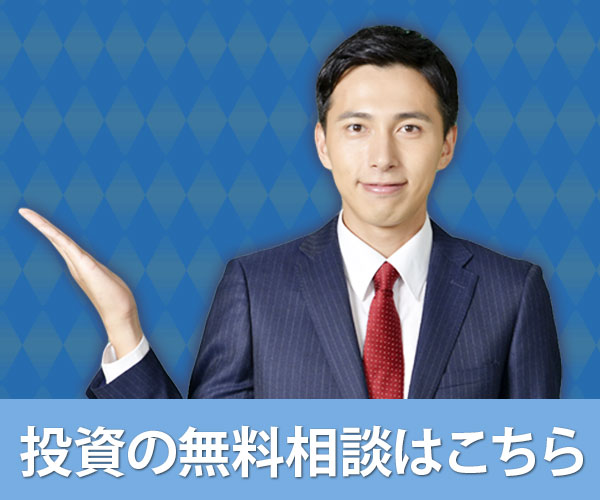- 2018-4-12
- 生命保険

生命保険契約において被保険者、契約者、受取人全てが異なる人物になっている場合、受取時に贈与税が課せられます。
贈与税は他の課税区分に比べ税率が高いため多くの税金を支払うことになります。受取時の税金を少しでも軽減するために、贈与税の控除について詳しく知っておく必要があります。
【贈与税の基礎控除を活用】
贈与税を節税するための方法として、非課税枠を活用するというものがあります。
贈与税は、1月1日から12月31日までの間に取得した財産の合計額から一人あたり基礎控除の110万円を差し引いた金額に対して課税されます。ですから年間の保険受取金の合計額が110万円に満たない場合は、贈与税がかかりません。
生前贈与を活用し、110万円を毎年贈与するという方法は贈与税の節税に大変有効です。
ただし、これは1人110万円までの非課税枠ですので他の方からも贈与を受けた場合には110万円を超えるため贈与税が課せられます。110万円を超えた場合には、税務署に確定申告をする必要がありますので覚えておきましょう。
【生前贈与を使うメリット】
では生命保険で生前贈与を活用するメリットはどのようなものがあるのかみてみましょう。
突然に発生する相続に対して、換金性の高い現金を保有しておらず、不動産しか保有していない場合は土地や建物を売却して換金するしかありません。しかし、生命保険の生前贈与を活用すれば不動産を売却せずに相続税を支払うことができます。
また、上記のように年間110万円までは税金がかかりませんので節税の効果が期待できます。
ただし、毎年同じ時期に同じ金額を継続的に受領していた場合、税務署に最初からまとまったお金を贈与するつもりだったと見なされてしまい多額の税金を支払うことになりますので注意しましょう。
これらのリスクを回避するためには、あらかじめ贈与契約書を作成しておく必要があります。
【まとめ】
生命保険は、契約者、被保険者、受取人によって課せられる税金が異なります。特に贈与税が課せられる場合、税率が最も高く高額な税金を支払う事にもなりかねません。
しかし、生命保険は活用次第では相続時、贈与時など税金の節税ができたり、不要な相続争いを回避できるなど多くのメリットがありますのでしっかりと活用しましょう。
【生命保険金が非課税になる方法】
生命保険金が非課税になる保険の加入方法は相続税となる契約です。この場合、契約者と被保険者が同一人物で受取人が子供や、配偶者などの場合です。生命保険金受取で相続税が課せられる場合、法定相続人一人につき500万円の非課税枠が設けられています。
非課税枠の計算式は下記のようになっています。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
例えば、相続人が妻と2人の子供だった場合500万円×3=1,500万円までが非課税枠となり1,500万円までは税金が掛かりません。